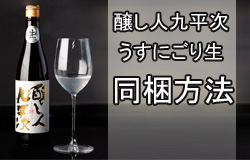広島県の酒蔵『相原酒造(雨後の月)』から社長の相原章吾氏を迎えた社内セミナーが開催されました。近年、各種日本酒コンクールへの上位入賞で注目を集める相原酒造。その酒造りに込めた想いや、皆様に美酒を届けるための試みについて、オンライン店スタッフもお話を伺ってきました。

● 若き社長の出発点
相原酒造の社長、相原章吾氏は1992年生まれの32歳。若手蔵元としてこれからの日本酒業界を牽引する存在です。元々、家業である酒蔵に関心がなかった章吾氏が日本酒に興味を抱いたきっかけは、友人の誕生日祝いのために実家から送ってもらった1本の日本酒でした。「その日本酒を飲んだ瞬間、『今まで飲んだ液体のなかで1番美味しい!』と衝撃を受けた」と話す章吾氏の言葉には、当時の想いが溢れていました。その日本酒が、当時開催されたSAKE COMPETITION 2013 の純米酒部門で1位を獲得した『雨後の月 特別純米 山田錦』だと知り、家業への興味が膨らんだそうです。


とはいえ、当時は別のキャリアを選択。大学卒業後はIT業界に身を置いていましたが、コスト競争の激しい業界で働くうち、次第に『安さではなく付加価値を求めるモノづくり』をしたいと考え始めるように。そんな2017年頃、父親から突然「いつ帰ってくるんだ!」という連絡を受け、実家の酒蔵を継ぐことを決意します。「やるなら製造から手掛ける蔵元杜氏になる」という意気込みで日本酒造りをスタートしました。
● ブランド継承と洗練
家業を継いだ章吾氏が直面したのは、経営難の蔵を継いで新たなブランドを立ち上げ再建していくという、書籍でよく見るような逆境のストーリーではありませんでした。むしろ借金はなく、ブランド認知度も高く、最先端設備を備え、有力な酒販店と取引もある順風満帆な状況だったのです。そのため「自分は先達が培ってきたものを継承・洗練させていく世代だ」と感じたと言います。
相原酒造にとって最も重要になるのが、メイン銘柄『雨後の月』の継承です。「上品、美しい、透明感」を味わいのキーワードとし、「雨上がりの月が夜空を美しく照らす情景美」を表現する『雨後の月』は、現在35種類ほど展開しています。このラインナップの高いクオリティを受け継いでいくには、「米・水・技術」がキーポイントになると章吾氏は強調します。
◇ 原料米のこだわり
相原酒造では山田錦や雄町、愛山のほか、八反錦や千本錦といった広島県内の優良品種も使用しています。精米歩合の違いも含めると取り扱うお米は約35種類にのぼり、すべて品質の高いものにこだわって仕入れていると言います。作り手として「最も品質の良い米を使っておいて日本酒の出来栄えが悪くなることは許されない」とプレッシャー材料にしているそうです。このストイックな姿勢が、美味しい日本酒を生み出しているのでしょう。最近では特に『雨後の月 純米大吟醸 白鶴錦』に手ごたえを感じたとのこと。
◇ 野呂山の水
日本酒造りにおいて技術も重要ですが、章吾氏は「水」も同じくらい重要だと感じています。技術ではコントロールできない口当たりや味わいのバランスに影響を与え、品評会で上位に進むお酒の間にあるほんのわずかな差を生み出すのが「水」ではないかと話します。相原酒造の豊富なラインナップのお酒がどれもバランスのよい出来栄えとなる秘訣も、蔵の程近くに位置する野呂山から生まれる地下水の懐の深さにあると言います。水という資源がいかに大事で、日本酒がどれほど土地に根差しているのかを感じさせられます。
◇ 技術と感性の継承
安定して酒質の良い多種多様な日本酒を造りだせるのは、相原酒造を支える蔵元のレガシーと呼ぶべき先達3人(現会長:相原準一郎氏 / 杜氏:堀本敦志氏 / 副杜氏:大西淳一氏)の天才的な技術や感性があってこそ。これらを一挙に継承する立場の章吾氏は、蔵に入って7年。「大体のことは7割ぐらいできると思っているけど、あとは実際に杜氏を務めてみないとわからない」と話し、偉大な先達からの継承という大役を背負いながらも近い将来に務める杜氏というポジションにワクワクしている様子がうかがえました。


◇ これから造るお酒の方向性
継承の先に、今の食中酒を超えるクラシックかつ本格的な味わいを追求していきたいと話す章吾氏。求めるのは「吟味(ぎんあじ)」。それは剛と柔、派手さと上品さ、繊細かつ大胆といった異なる要素が絶妙なバランスでまとまる日本刀のようなイメージだと話します。
● オリジナリティを求めた挑戦
『雨後の月』を継承する一方で、章吾氏が自身で新たに立ち上げたのがUGO(ユージーオー)シリーズ。それは2019年、余剰の酒米をもとに、自分の日本酒造りの出発点である「雨後の月 特別純米 山田錦」をアレンジして造ったことからスタートしました。このシリーズで章吾氏は、これまでと異なる製法で『雨後の月』にない新しい味わいを追求するとともに、自分のイメージする日本酒をゼロから造り上げる経験を積むことで、ブランディングに挑戦しています。
・ロゴが表現するUGOシリーズ
UGOシリーズを象徴するロゴは、宝石のようなバランス美を表現していますが、実は畳んだ傘のシルエットもモチーフとなっているそう。雨後の『月』と対になる、雨上がりに『太陽』が出ている爽やかな昼をイメージしており、雨後の月とは異なる新しいお酒であることを表しています。

・造りのこだわり
UGOシリーズの造りでは「広島県産米」「真吟精米」「14度原酒」の3つのこだわりを持っています。個性豊かな広島県産米を、お米のポテンシャルを引き出す真吟精米で磨き、甘みと酸味のバランスが整う14度原酒に仕上げることで、低温から常温まで美味しく飲み続けられる「吟味」を表現しています。
・一期一会の味
1年目は設計の確立、2年目は米違いによる個性の追求、3年目はブレンドの試行といったように、毎年異なるコンセプトのもとUGOシリーズは造られています。そのため、出来上がる味わいはリリース毎に様々で、タイミングを逃すと二度と飲むことができない一期一会の味となっています。
まさに章吾氏の日本酒造りの歩みを反映する貴重な一品といえるUGOシリーズ。タンク1本ずつ試行錯誤の中で造る味わいをお楽しみください。
●相原章吾氏が求める理想の日本酒
まだまだ試行錯誤の中で、最終的に造り上げたいお酒のビジョンはハッキリ見えていないという章吾氏ですが、理想のお酒について次のように語ってくれました。
「味って、いつ/どこで/誰と飲むかで感じ方が変わると思うんです。けれども、そういった要素は関係なく、ふっとした瞬間に『美味い』って純粋に感じてもらえるお酒を造っていけたらいいなとは思っています」
その言葉には、かつて自分が日本酒に興味を抱いた瞬間のように、何気なく口に含んだ時の感動を飲み手に感じてもらいたいという強い思いが込められていました。
今年150周年の節目を迎える相原酒造。章吾氏が今後『雨後の月』をどのように洗練させて求める吟味を生み出すのか、UGOシリーズという挑戦を重ねた先にどんなオリジナリティ溢れる日本酒を造りあげるのか、期待に胸が高鳴りますね。